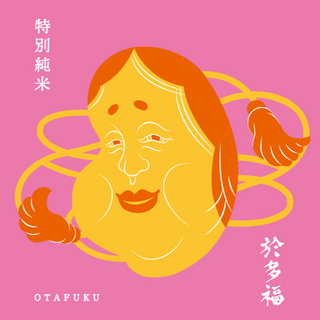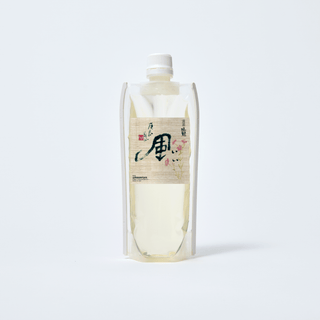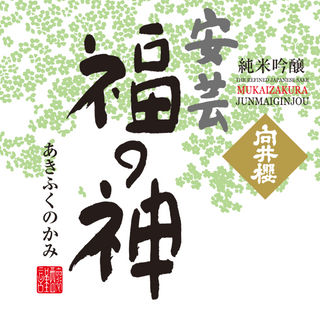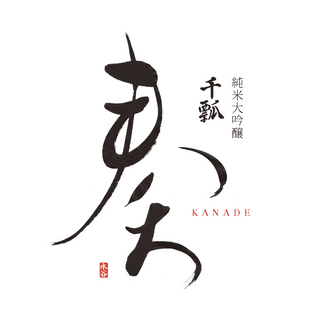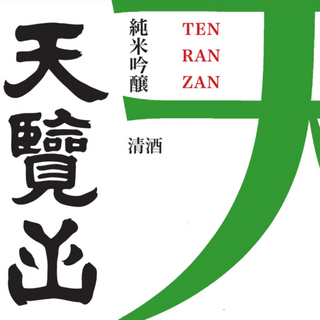日本酒は、原料を発酵させて作る「醸造酒」です。
では、同じ醸造酒のビールやワインとは、どのように違うのでしょうか。
実は、原材料の違いが作り方の違いに直結しているのです。
そして日本酒は、世界的に見ても非常に特殊な醸造方法で作られています。
この記事では、日本酒とビール・ワインとの大きな違い、日本酒の細かい製造工程について解説します。
日本酒とビール・ワインとの大きな違い
まず、日本酒とビール・ワインとの違いを見ていきましょう。
大きな違いは、次に挙げる2つになります。
原材料が違う
周知の事実かもしれませんが、日本酒とビール・ワインでは原材料が違います。
- 日本酒……米
- ビール……麦芽
- ワイン……ぶどう
他に副原料を使用する場合もありますが、主原料については上記の通りになります。
実は、この原材料の違いがとても重要な違いに結びついているのです。
作り方が違う
先ほど挙げた原材料の違いで、製造方法が大きく変わります。
醸造酒は、アルコール発酵(酵母菌が糖分をアルコールと二酸化炭素に分解すること)によって作られます。
ワインの場合、原材料のぶどうに糖分が含まれていますので、それを分解するだけでアルコールを得られます(単発酵)。
しかしながら日本酒とビールの原材料には、糖分は含まれていません。
よってアルコール発酵させるには、原材料中のでんぷんを糖に変える必要があります。
ビールでは、麦芽のでんぷんを酵素によってすべて糖化させたのちに、アルコール発酵に進みます(単行複発酵)。
日本酒の場合、糖化と発酵を順番にするのではなく、同時に並行して進めていくのです(並行複発酵)。
この「並行複発酵」は東アジアに集中してみられる独特な製法となっており、これがビール・ワインとの決定的な違いとなっています。
日本酒の製造工程

(参考)富士高砂酒造のご紹介
ここからは、日本酒の一般的な製造工程を説明していきましょう。
一部の大手メーカーでは、一年通して日本酒を仕込む「四季醸造」が実施されています。
しかしながらかかるコストが膨大ですので、秋から春にかけて仕込む「寒仕込み」をする酒蔵が大半で、今でも主流となっています。

(参考) https://jp.sake-times.com/infographics-free-download
精米

最初の工程は、原料米の表面をみがいて削る精米の作業です。
この精米の歩合によって、できあがる日本酒の風味が大きく変化します。
たとえば食用米の精米歩合は、約90%(10%を削る)です。
これが酒造米になると本醸造酒で70%以下、吟醸酒で60%以下、大吟醸酒では50%以下となります。中には精米歩合10%などというものも。
精米歩合が高い(削る部分が多い)と、一般的に雑味の少ない華やかなお酒に仕上がります。
精米したての米は割れやすく水分量が減っているため、2~3週間冷暗所で保管する「枯らし」を実施します。
洗米・浸漬
枯らしの終わった米を洗う作業です。
多くの場合は機械で洗米しますが、精米歩合の高い米は割れを防ぐため手洗いする場合もあります。
洗米した米は、吸水させるためすぐに水につけます。
気温や湿度、精米歩合などさまざまな条件によってつける時間が変わるので、細心の注意を払って管理しなければなりません。
秒単位で管理している酒蔵もあるほど。
つけ終わった米は水を切り、水分を落ち着かせるため一晩ほど「枯らし」をします。
蒸米(じょうまい)

枯らしの終わった米を、「甑(こしき)」という蒸し器に入れて蒸し上げます。
米を炊かずにゆっくりと蒸すことで、米の表面は硬く内側が柔らかい、菌の繁殖しやすい状態となるのです。
蒸米の出来が完成する日本酒の品質に多大な影響を与えるので、気の抜けない大変重要な作業です。
食用米とは違い、外は硬く内が柔らかいパラパラとほぐれるような蒸米を目指して作り上げます。
蒸しあがった米は麹(こうじ)・酒母(しゅぼ)・醪(もろみ)として使うため、蒸米は数回に分けておこなわれます。
製麹(せいきく)

(参考) https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/know/99
麹用の蒸米に、黄麹菌を植え付けて米麹を作ります。
麹の主な役割は、次の3つです。
- 酒母や醪に対してでんぷんを糖化する酵素の供給
- 酵母の栄養分の供給
- 酒質に影響する成分の供給
麹造りの期間は、約2日間。
麹室(こうじむろ)と呼ばれる部屋で、温度と湿度を保つように調整しながら作っていきます。
菌をまんべんなく行きわたらせるため、何度も揉んだりほぐしたりを繰り返しながら仕上げます。
酒母造り

(参考) https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/featured/186
蒸した米に水と米麹、酒造用の酵母を加えて酒母(酛(もと)とも呼ばれる)を作成します。
酒母とは、醪の発酵をスムーズにするために酵母を大量に培養させたものです。
酒母を作る際、雑菌や野生酵母(空気中に存在する酵母)が混入すると品質が劣化してしまいます。
それを防ぐためには、乳酸が欠かせません。
乳酸によって雑菌や野生酵母を駆逐し、酒母の品質を守ります。
醸造用乳酸を加えてつくる酒母は「速醸系酒母」、乳酸菌から乳酸を生成させてから酵母を加える酒母は「生酛系酒母」と呼ばれます。
酒母完成までの期間は、速醸系酒母は約2週間、生酛系酒母は約1か月です。
醪造り

(参考) https://www.shibatabrewery.com/sake/make_flow/
酒母に水と蒸米、麹を加えて醪を作成します。
醪の仕込み期間は4日間。
一度に大量の原料を入れると酵母の増殖が追い付かず、雑菌が繁殖してしまいます。
そのため、3回に分けて仕込む「三段仕込み」という方法をとるのが一般的です。
初日に酒母に対して全体の2割弱の原料を加える「添え」と呼ばれる作業をします。
2日目は酵母の増殖を進めるためにおいて置き(「踊り」と呼ばれます)、3日目に3割程度の原料を加える「仲」という作業、4日目に残りすべての原料を加える「留」の作業をして醪の仕込みは終了です。
3回以上に分けて仕込む場合もあり、回数によって「四段仕込み」「十段仕込み」などと呼ばれます。
発酵
完成した醪を、約2週間から1か月かけて発酵させていきます。
この時にタンクの中では、でんぷんの糖化と糖のアルコール発酵が同時になされる「並行複発酵」が進んでいます。
発酵中は熱が発生するので、適切な温度管理が大切です。
上槽(じょうそう)

(参考) https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/featured/206
発酵を終えた醪は搾られ、液体と固体に分けられます。
「袋詰めした醪を自動圧搾機にかけて横から搾る」「袋詰めした醪を上から圧力をかけて搾る」「袋を搾らずに吊り下げて落ちてきた液体を集める」など、さまざまな方法が取られます。
上槽の際に出てくる搾りかすが、「酒粕」です。
滓引き(おりびき)・ろ過
搾り終えた後の液体には、滓と呼ばれる細かい固形物が残ります。
これを10日ほど置いて沈殿させて、上澄みを取るのが「滓引き」の作業です。
さらに完全に滓をのぞくためにフィルターにかけてろ過しますが、酒本来の香味を活かすためにろ過しない場合もあります。
火入れ
滓引き・ろ過をしてもまだ酵素や微生物が残っており、それらがまた活動すると味や品質が変わってしまう恐れがあります。
その活動を止めるために、熱を加える作業が「火入れ」です。
火入れは貯蔵前と出荷前の2回実施されるのが基本となります。
火入れしない酒を「生詰め酒」「生酒」「生貯蔵酒」として販売する場合もあります。
貯蔵

(参考) https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/featured/214
できあがった原酒に水を加えて、タンクで数か月間貯蔵して熟成させます。
数か月の貯蔵を経ると、原酒の荒々しさが取れてまろやかな味わいになります。
なぜまろやかになるかのメカニズムについては、まだ完全には解明されていません。
通常は春から夏にかけて貯蔵しますが、搾ったお酒をそのまま「あらばしり」「しぼりたて」として販売する商品もあります。
仕上げ・完成
出荷前に再度火入れをして、瓶やパックに詰めて出荷します。
このように、長い期間と手間暇をかけて日本酒は作られます。
日本酒の仕込み期間は、寒仕込みの場合は秋から春にかけておよそ5か月間です。
しかしながら夏の間も、他の商品の仕込みや米作りなど、酒蔵の仕事は一年中なくなりません。
まとめ
ここまで、日本酒とビール・ワインとの違い、日本酒の一般的な製造工程について説明してきました。
日本酒は「並行複発酵」という特殊な製法で作られる、世界的に見ても珍しいお酒になります。
発酵方法や製造工程を知れば、さらに深く日本酒を楽しめるのではないでしょうか。