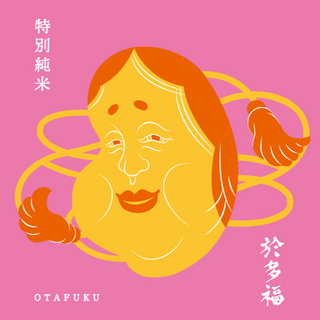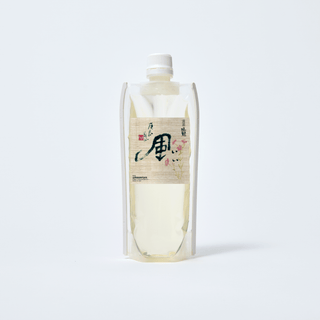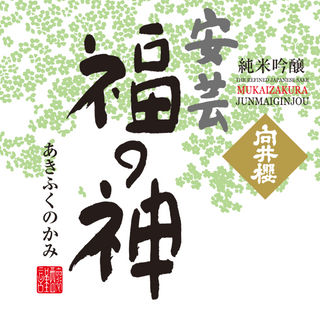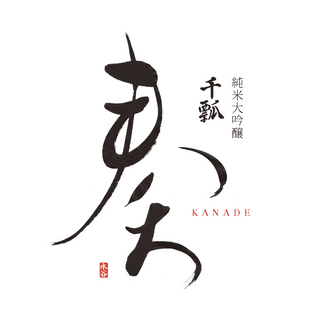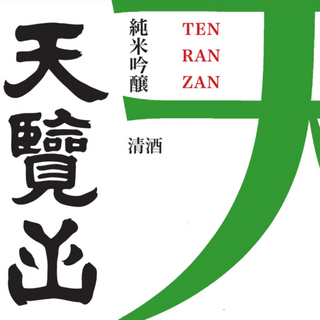「イカ徳利を自作で作ってみたい!」
「自分で作ったイカ徳利で日本酒が飲めたら最高!」
こんなふうに思っていますか?
イカ徳利は、酒器として使ったあとにおつまみとして食べられるという優れもの。
イカ徳利◎#佐渡の日 #佐渡を世界遺産に! #いかとっくり pic.twitter.com/ACjhdCOZgD
— 室岡ひろし (@mro1118) March 9, 2022
中には、イカ徳利好きが高じて自分でイカ徳利を作ってみたい!と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
イカはスーパーで手軽に買えますから、一度チャレンジしてみたいと思われる気持ち、わかります!
そこで今回は、イカ徳利の作り方を詳しく解説していきます。
また、美味しく日本酒が飲めるイカ徳利の使い方や、どんなふうに味わいが変わるかという魅力についても迫っていきたいと思います。
イカ徳利の作り方。自作にチャレンジしてみよう
できた♪
— 🔰く🔰ろ🔰た🔰む🔰 (@matazerokaratam) July 24, 2020
釣ったスルメイカで作ったイカ徳利🦑🍶
めっちゃ不格好だけどちゃんと立つし、中にお酒も入れられるよ♪ pic.twitter.com/pT7xVM8Cio
嗚呼、自作のイカ徳利が尽きてしまった。また来年、日差しの強い日に会おう
— ヒロキチ@VRchat (@VRherokichi) September 23, 2020
イカ徳利は、非常に手間のかかる工程を経て造られています。
そのため生産者自体が非常に少なく、製造しているのは「鞍岡商店」の一軒しかありません。
通常は専用の機械を用いて空気を入れることで成型したり、プレスしたりして作られています。
ですが、アマチュアレベルであれば、イカ徳利を自宅で作ることもできるのです。
【イカ徳利の作り方】
- まずはイカを用意し、内臓と足を取り除いた状態にします。
- 次に、表面の皮をはぎ、良く水気を切ります。
- その後、筒状に成型するため、キッチンペーパーの芯などにラップを巻きつけたものを奥まで差し込みましょう。
- うまく形を整えたら、陰干しでイカの水分が抜けて堅くなるまで乾燥させて出来上がりです。
【コツと注意点】
イカの剣先は切り落としてもそのままでも問題ありませんが、切り落とす場合は慎重に!切りすぎて穴が開いてしまっては元も子もありません。
また、乾燥が上手く行かない場合もあります。
その場合には、イカの頭を押し込むことで、いかの裏と表をひっくり返し、よく乾燥させてください。
イカ徳利の上手な使い方
イカ徳利ができたら、早速日本酒を入れてみましょう!
倒れないようにコップやグラスにイカ徳利を入れてから注ぐのがコツです!
イカ徳利に日本酒を入れたら、お猪口に注いで飲みます。
飲んでいる間も、倒れないようにグラスに入れておくのがおすすめです。
自作したイカ徳利で飲む日本酒は、また格別なはずです。
イカ徳利で変わる日本酒の味わい
🦑イカ徳利🍺焼けました😋 pic.twitter.com/GSt7H1U1FM
— あっきーのパパ (@uwajimatsunoura) March 5, 2022
イカ徳利で日本酒を飲むと、一般的な陶器製や金属製の徳利とはまた違う日本酒の味わいを楽しむことができます。
イカに含まれる塩気やいかそのものの風味が日本酒に移り、スモーキーで濃厚な味わいに変化します。
もっとイカの香りを味わいたい時には、日本酒を注いで1時間ほど置いておくと鮮烈な海の味を味わうことができるでしょう。
また、イカ徳利に日本酒を注ぐと味が変わるのはもちろんですが、乾燥したいかの色素が染み出て僅かに黄色みがかります。
常温でも冷酒でも熱燗でも、好みの温度の日本酒で問題ありませんが、おすすめしたいのは熱燗です。
冷酒や常温を注いだ場合と異なり、さらに濃いイカの風味を楽しむことができます。
また、イカ徳利は1度使って終わりではありません。
2回から3回は日本酒を入れて楽しむことができます。
飲み終わった後は、イカ徳利を炙って食べるのも良いですね。
1つで何度も楽しめるのがイカ徳利の魅力です。
イカ徳利の発祥って?
発祥には諸説あります。
長崎県の壱岐郡郷ノ浦町が発祥の地であるとしている説や、岩手県宮古市で故・山内康平氏が考案したという説などさまざま。
玄界灘や三陸沖など、いずれも海産物が豊かな沿岸部で製造されており、材料として用いるイカも、水イカや真イカにするめイカなどいくつかの種類のイカが存在しています。
メーカーの販売店はもちろん、全国のお土産所などで販売されており、地域の特産品として販売されているケースも。
新潟県の佐渡汽船新潟港ターミナル内の売店では、佐渡島で造られたイカ徳利をその場で購入することができます。
ちなみに、イカ徳利は特許・実用新案が登録されており、北海道の函館で海道の海産物、主に近海産のイカ・タコを主体とした食品製造加工を行っている「トナミ食品工業株式会社」の取締役社長・利波英樹氏が特許を持っています。
オリジナルのイカ徳利で晩酌を楽しもう
イカ徳利 pic.twitter.com/gepnLx7AbK
— #こっことぅわん。🐣@ゆきみのここ (@k20190216) December 31, 2020
イカ徳利の作り方は以下の通りです。
- 内臓と足を取る
- 表面の皮をはぎ、良く水気を切る
- 筒状に成型する
- 陰干しで乾燥させる
酒器として日本酒を注いでも、おつまみとして食べても美味しいイカ徳利。
ユニークな見た目と相まって、話のタネにもなりますね。
ぜひ、自作でイカ徳利づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。